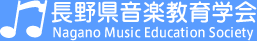令和7年度長野県音楽教育学会長挨拶
歴史に学び、今という時代に生きる子どもたちをとらえ、未来へとつなげる
令和7年度の長野県音楽教育学会の活動がスタートしました。音や音楽を学ぶことの楽しさや喜び、そしてワクワク感を一つでも二つでも広げられるよう、本学会の事業を展開して参りたいと存じます。
さて、新年度のスタートに当たり、「歴史に学び、今という時代に生きる子どもたちをとらえ、未来へとつなげる」と題して、「歴史に学び」「今という時代に生きる子どもたちをとらえ」「未来へとつなげる」という3つの視点からお話をさせていただきます。
<歴史に学び>
長野県音楽教育学会の歴史は長く、昭和27年に発足しました。今年で73年目を迎えます。都道府県レベルで、これだけの歴史を持つ学校音楽教育に関わる組織は全国的にも珍しいです。 当時の関係者の学校音楽教育にかける情熱と意識の高さが伝わってくるのですが、実は、本県では、明治時代からの先人たちの功績が大きいのです。 例えは、日本の学校音楽教育の礎を築いた伊沢修二(高遠出身)と神津仙三郎(小諸出身)の活躍、全国に先駆けてバイオリンを用いて歌唱指導を行った能勢栄(長野県師範学校初代校長)などがいます。 また、全国に先駆けて、明治10年代にはバイオリンを、明治20年代にはオルガンを、明治30年代にはピアノを用いての音楽指導が行われたという記録もあります。 先人たちがチャレンジングな精神をもち、学校音楽教育を開拓してきたという歴史は誇るべきことであります。
<今という時代に生きる子どもたちをとらえ>
著作家・経営コンサルタントの山口周さんは、我が国は「登山社会」から「高原社会」へと移行してきていると指摘しています。 同じ山頂を目指し、いち早く辿り着こうとするような競争社会は終わり、それぞれに大切にしたいことを自ら求めることができる時代に入っているということです。 このことを学校音楽教育に重ねると、例えば、西洋音楽的な発想のみで技能面で競ってきた時代から、もっと穏やかに、それぞれの人にとっての価値を見出せる音楽との出会いを大切にする時代に入っていると考えられます。 「高原社会」では、社会における芸術が果たす役割もこれまで以上に大きくなります。 最近話題の部活動の地域展開の考え方も、「登山社会」から「高原社会」への発想と重なるところがあります。
<未来へとつなげる>
部活動の地域展開が求められている理由の一つに、これからの少子化の時代においても持続可能にするためという理由があります。 本学会においても、持続可能にするという視点から、長野県音楽教育研究大会、長野県合唱大会、合奏コンクールなどの在り方を模索していかなければなりません。 そして、音楽科授業ついては、学習指導要領の次期改定に向けての動きが活発化しています。 これからの新しい時代に生きる子どもたちに、どのような力が求められるのか、時代の動きに目を向けつつ、本学会においても、未来につながるような活動を展開し、未来への新たな方向性を検討しなくてはなりません。
以上、3つの視点からお話をさせていただきました。 過去、現在、未来へと歴史はつながるのですが、新しいアイデアの創出が歴史を動かしてきました。 新しいアイデアの創出といえば、それはまさに芸術的な行為の本質でもあります。 本学会におきましても、、ワクワクするような新しいアイデアを創出しながら、会員の皆さまと共に歴史を前進させることができればと願っております。 本年度も皆さまのお力添えをどうぞよろしくお願いいたします。
長野県音楽教育学会会長 齊藤忠彦
Copyright(C)2010 長野県音楽教育学会(Nagano Music Education Society)